「英国のEU離脱は経済危機と言うより、欧州瓦解への政治シナリオだ」
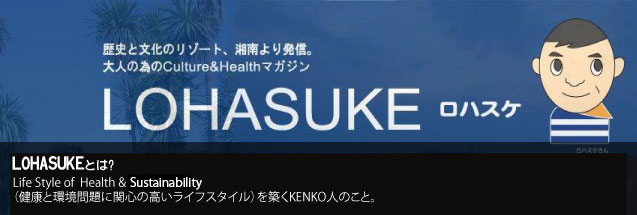
|
英国の欧州連合離脱が、世界的経済危機を恐れる投資家・投機家のセンチメント反応をよび、 それに輪をかけたUHTF(超高速取引)の所為もあり、不動産売買や株式・為替の 大幅変動を呼んでおります。 もっとも、“長期投資家”のウォーレン バフェット氏の明言「金融市場を短期的に揺さぶるのは、 市場の95%にも上る“短期投機家”の仕業」であり 、 同じく長期投資家のジム ロジャーズ氏の言「英離脱騒動が収まるまで、 1~2年間は株を買わない」も併せて考えると、マスコミや一部経済評論家の 過剰反応ぶりが色あせて見えてきます。 日本株や円取引の三分の二が外国人であり、しかもその95%が、“超短期的投機家”が 占める訳ですから、まともな投資家は静観するのが筋でしょう。 いずれにせよ、英国の離脱交渉(条件闘争)は、まだ始まってもおらず、 これから二年間の猶予がある(どんでん返しも有り得る)訳ですから、 この時点で経済問題に焦点を当てるのは、妥当な議論とは思えません。 今回の騒動は、英国発欧州政治の瓦解への道程と見ると、色々と見えてくるものがあります。 まず、英国与党の内部分裂に業を煮やしたキャメロン首相が、そもそも国民投票に かける必然性もなかったのに、(勝てると読み違え)敢えてEU離脱か、残留かの 二者択一選挙に丸投げしてしまった大ポカが挙げられます。 賛否が分かれ国民を二分しそうな選挙の場合、 「アビリーンの逆説(経済学者ジェリー ハーベイによる集団思考の危険性に関する社会心理学説で、 人は、しばしば群集心理に巻き込まれ、本来望んでいないことに同調し、 結果を見て後悔するという社会心理学説で、経営者や政治家が熟知しておくべきこと)」とか、 経済学者ケネス アローの選択肢を三つ以上とすべきとする「不可能性定理」や他にも、 コンドルセの投票方法(選好順序を読み込む)などを配慮しておれば、結果は違ったはずです。 ましてや、離脱派の扇動的キャンペーンに行き過ぎというか、虚偽の数値による デマゴーグ(英の対EU出費額のみを取り上げ、EUからの還付受給額を隠ぺいした)が あったようで、無責任な政治家とマスメディアの大罪が、今改めて問われています。 元来、民主主義の原理とは、“最大多数の最大幸福”を希求する(多数決のハードルを上げる)ので あって、僅か4%の賛否の差で、国家の行方を決めると、何れに転んでも双方に不満を残す筈でしょう。 賛否の差をせめて20%以上と見る(60%対40%)とか、差が10%以内なら、 議会へ決議を戻すとか、手の打ちようがあったのではないでしょうか。 現に、党首を投げだしたキャメロン氏の後任に、同じ残留派の女性党首候補のテリーザ メイ内相が選ばれ、 首相にもなりそうなことからして、また離脱派のジョンソン前ロンドン市長が党首選不出馬を決め、 独立党のファラージ党首が辞任するなど、英国政治家たちの責任倫理が問われる上に、 史上最低の泥試合とか筋書きのない三文ドラマと揶揄される英国政治の大混迷はまだまだ続きそうであり、 英国民の悲劇を垣間見る次第です。 残留派のロンドン市民ほか若年層、スコットランド、ウェールズ両州などの今後の動き次第で、 UK(英連合王国)分裂騒動になるやもしれませんし、ひょっとして、女王の出番があるかもしれません。 EU盟主の一端を担っていた英国発の激震に見舞われた欧州連合には、団結して取り組む力はなく、 残された盟主のドイツには、苦手の安全保障では、もとより及び腰であり、 ましてや英語圏の英連邦諸国と米国への橋渡しを失うことは、政治外交のみならず、 経済面でも大きなマイナス要因を抱えることになります。 EU第一の経済力を誇る独の一人勝ちに対する反感は、経済力の弱いフランス、 イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、東欧など日増しに広がっており、 その背景には域内主要国にナショナリズムを掻き立て、右翼ポピュリスト政党の跋扈伸長を 助長しているのが実情です。 [ある意味、米国トランプ旋風との共有性もあり]独の著名経済学者(氏名失念)が語ったように 「英のEU離脱劇の最大の敗者はドイツだ」と言うのがどうも欧州全域を覆いつつある空気のようです。 つまり 第二次大戦後生み出された、国連、EU(およびユーロ),グローバリゼーションなどの 国際化がすべての解決策だとする神話の崩壊現象の始まりであり、世界秩序のガードマン不在の 始まりであるとも言えそうです。 EUの難題は第一に、相次ぐテロを防げなかった移民、難民の中東イスラム圏課題で、 その要因となったシェンゲン宣言の見直しであり、第二が諸国間の財政力格差拡大に対する 金融政策の限界=ユーロの行き詰まりであると共に、第三にして、実は根強い反感の源泉と 言われるブルュッセルに本部を置く官僚たちの愚策で、現場感覚を欠く諸政策が、 あまりにも細則に拘り加盟諸国の現状に離反するケースが頻発していることだそうです。 このことから、英国の離脱折衝に重ねて、離脱乃至は条件闘争のドミノ現象がEU分裂騒動に 発展するのではないかと危惧する国際メディアの論評が増えつつあります。 一方、大西洋同盟(NATO)に関して触れると、英国の脱退こそ有り得ませんが、 既にウクライナ問題でロシアの進出を止められなかった (旧東独出身のメルケル女史の及び腰が取りざたされた)ように、 有名無実化が始まっており、米国のオバマ弱腰外交に始まる“相対的衰退”がEUの “絶対的衰退”とも重なり、世界の安全保障の分野においても、露中の横暴や中東紛争、 国際テロの頻発に歯止めがかからなくなり、 世界秩序の守護神を欠く現象が当面続きそうな現状です。 12日にも、中国による南シナ海諸島占拠に対するハーグ条約の裁定が出ます。 その是非に関して、新たな世界の動きが加速されそうですから、自由主義陣営の再構築次第では、 欧州の中国依存(経済・金融面)に見直しの機運が出てくることも考えられます。 そもそも、EU統合は政治主導による経済統合だった訳ですが、 心理面ではキリスト教合州国構想と相いれない英国国教会が一線を画し、 英ポンドを保守堅持しユーロを受容しなかったところに、今回の騒動の種を宿していました。 (EU28ヶ国に対し、ユーロ19ヶ国)また民族風土面でも、長年の対立色が強い、 アングロサクソン系、ゲルマン系、ラテン系に独立色の強い北欧系と、遅れて加盟した 発展途上国中心の東欧系と、同床異夢が絶えませんでした。 英語圏自由経済マーケットへの窓口であり、ユーロと並ぶポンド金融為替市場が ドル圏との潤滑油になっていただけに、英国の離脱は他の加盟国の多くを目覚めさせ、 視座の転換に影響する可能性は大と見られます。特に目が離せないのが、フランス、 オランダ、デンマーク、イタリア、スペイン、ポルトガルの動きです。 いずれも、ドイツの足を引っ張りこそすれ、サポートに回る可能性が殆どない諸国なのです。 となると、今次の英国離脱問題は、単なる分水嶺ではなくなり、ドイツ主導のユーロを核とした 欧統合プロセスが、欧州再興の壮大な試みの終わりの始まりに向かうという 意味合いを帯びてくるでしょう。 (広告)
|
| ↑ページの先頭に戻る |
 本サイトが掲載する情報・画像等は、提携サイトの湘南情報サイト「ロハスケ」編集部より提供されています。 本サイトが掲載する情報・画像等は、提携サイトの湘南情報サイト「ロハスケ」編集部より提供されています。著作権は「ロハスケ」編集部に属します。 権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。 商業目的に記事を引用、転写する場合は、引用:一項30,000円、転写:50,000円となります。 Copyright NOGI-BOTANICAL All rights reserved. 本サイトが掲載する情報・画像等は、広告主の湘南情報サイト「ロハスケ」編集部より提供されています。著作権は「ロハスケ」編集部に属します。 権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。 |